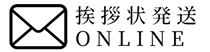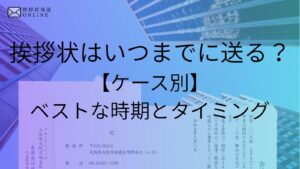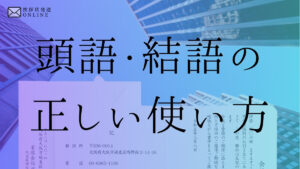10月・11月の季節の挨拶(時候の挨拶)文例集
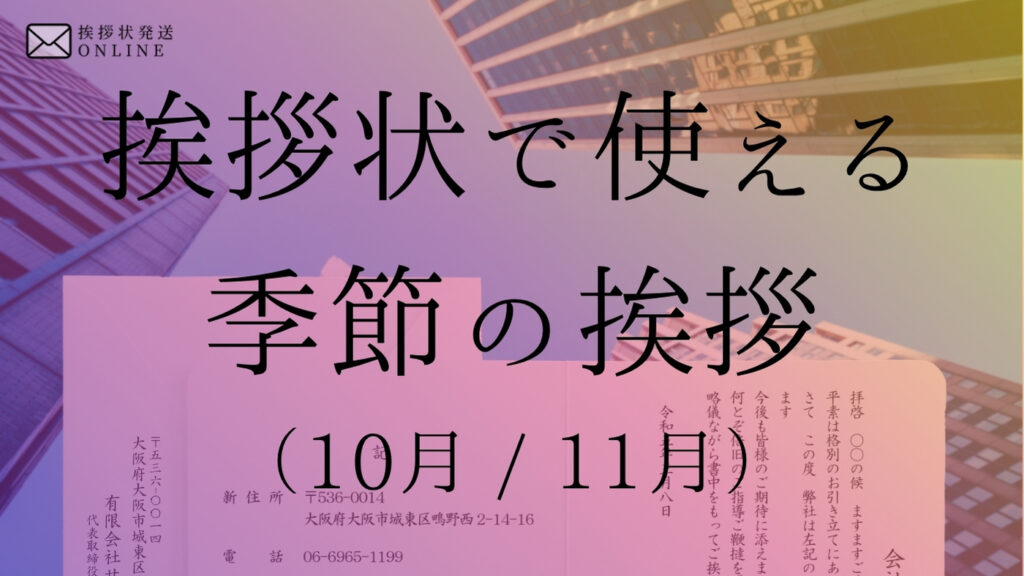
ビジネス文書や挨拶状では、書き出しに「時候の挨拶」を添えるのが一般的です。
季節感を大切にした言葉選びは、相手への礼儀であると同時に、日本独自の美しい文化でもあります。
ここでは、10月・11月に使える時候の挨拶をまとめました。
10月の時候の挨拶
初旬(10月上旬)
- 秋冷の候(しゅうれいのこう)
- 秋涼の候(しゅうりょうのこう)
- 爽秋の候(そうしゅうのこう)
👉 朝晩が涼しくなり、秋の爽やかさを伝える表現。
中旬(10月中旬)
- 秋晴の候(しゅうせいのこう)
- 菊花の候(きっかのこう)
- 紅葉の候(こうようのこう)
👉 スポーツや文化の季節を感じさせる言葉も使える。
下旬(10月下旬)
- 晩秋の候(ばんしゅうのこう)
- 霜降の候(そうこうのこう)
- 向寒の候(こうかんのこう)
👉 冬の気配を伝える挨拶が適する時期。
11月の時候の挨拶
初旬(11月上旬)
- 立冬の候(りっとうのこう)
- 菊花薫る候(きっかかおるこう)
- 深秋の候(しんしゅうのこう)
👉 暦の上では冬、でもまだ秋の趣を表せる時期。
中旬(11月中旬)
- 向寒の候(こうかんのこう)
- 小雪の候(しょうせつのこう)
- 霜寒の候(そうかんのこう)
👉 朝晩の冷え込みや霜のイメージを盛り込む。
下旬(11月下旬)
- 初冬の候(しょとうのこう)
- 寒気の候(かんきのこう)
- 師走近しの候(しわすちかしのこう)
👉 年末を意識させる季節感が好まれる。
時候の挨拶を使うときのポイント
- 頭語と結語をセットで使う(例:「拝啓」「敬具」)
- 季節の挨拶のあとに相手の安否を気遣う文を添える
- 例:「皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。」
- 文例は硬すぎないように、相手や用途に応じてアレンジする
まとめ
- 10月は「秋から冬への移ろい」を、11月は「冬の到来」を意識した表現が適切。
- 文例をそのまま使うだけでなく、相手や用途に合わせて調整することで、より誠意が伝わります。
時候の挨拶の関連記事
- 8月・9月の時候の挨拶文例集|残暑・初秋に使える言葉と文例
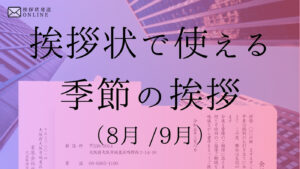 8月・9月は、真夏の暑さから秋の気配へと季節が移り変わる時期。ビジネスでもプライベートでも、季節に合わせた言葉… 続きを読む: 8月・9月の時候の挨拶文例集|残暑・初秋に使える言葉と文例
8月・9月は、真夏の暑さから秋の気配へと季節が移り変わる時期。ビジネスでもプライベートでも、季節に合わせた言葉… 続きを読む: 8月・9月の時候の挨拶文例集|残暑・初秋に使える言葉と文例 - 6月・7月の時候の挨拶文例集|梅雨から盛夏にかけての挨拶に
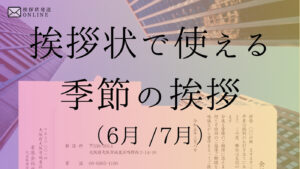 6月と7月は、季節の移ろいを感じる時期。雨の季節から、日差しの強い夏へと変わるこの頃は、相手の体調や季節感を気… 続きを読む: 6月・7月の時候の挨拶文例集|梅雨から盛夏にかけての挨拶に
6月と7月は、季節の移ろいを感じる時期。雨の季節から、日差しの強い夏へと変わるこの頃は、相手の体調や季節感を気… 続きを読む: 6月・7月の時候の挨拶文例集|梅雨から盛夏にかけての挨拶に - 4月・5月の時候の挨拶文例集|新年度・春のビジネス挨拶に
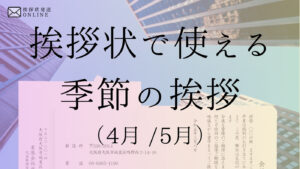 4月と5月は、新しい出会いや始まりにあふれる季節。入学・入社・異動・転勤など、挨拶状やお礼状を送る機会が多くな… 続きを読む: 4月・5月の時候の挨拶文例集|新年度・春のビジネス挨拶に
4月と5月は、新しい出会いや始まりにあふれる季節。入学・入社・異動・転勤など、挨拶状やお礼状を送る機会が多くな… 続きを読む: 4月・5月の時候の挨拶文例集|新年度・春のビジネス挨拶に - 2月・3月の時候の挨拶文例集|早春のご挨拶にぴったりの言葉
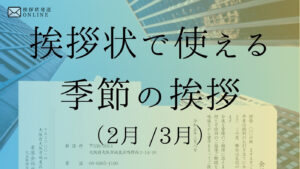 寒さの中にも春の兆しを感じる2月と3月。この時期の挨拶状には、「寒さを気遣う言葉」と「春を喜ぶ表現」を上手に取… 続きを読む: 2月・3月の時候の挨拶文例集|早春のご挨拶にぴったりの言葉
寒さの中にも春の兆しを感じる2月と3月。この時期の挨拶状には、「寒さを気遣う言葉」と「春を喜ぶ表現」を上手に取… 続きを読む: 2月・3月の時候の挨拶文例集|早春のご挨拶にぴったりの言葉 - 12月・1月の時候の挨拶文例集|冬のご挨拶・年末年始に使える表現
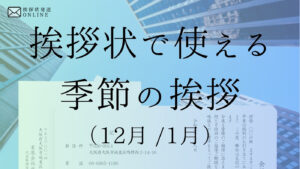 12月・1月は、一年の締めくくりと始まりを告げる特別な季節。ビジネス・個人を問わず、丁寧なご挨拶を交わす機会が… 続きを読む: 12月・1月の時候の挨拶文例集|冬のご挨拶・年末年始に使える表現
12月・1月は、一年の締めくくりと始まりを告げる特別な季節。ビジネス・個人を問わず、丁寧なご挨拶を交わす機会が… 続きを読む: 12月・1月の時候の挨拶文例集|冬のご挨拶・年末年始に使える表現 - 10月・11月の季節の挨拶(時候の挨拶)文例集
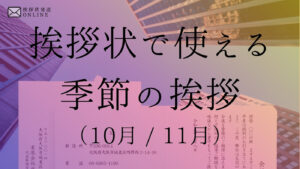 ビジネス文書や挨拶状では、書き出しに「時候の挨拶」を添えるのが一般的です。季節感を大切にした言葉選びは、相手へ… 続きを読む: 10月・11月の季節の挨拶(時候の挨拶)文例集
ビジネス文書や挨拶状では、書き出しに「時候の挨拶」を添えるのが一般的です。季節感を大切にした言葉選びは、相手へ… 続きを読む: 10月・11月の季節の挨拶(時候の挨拶)文例集